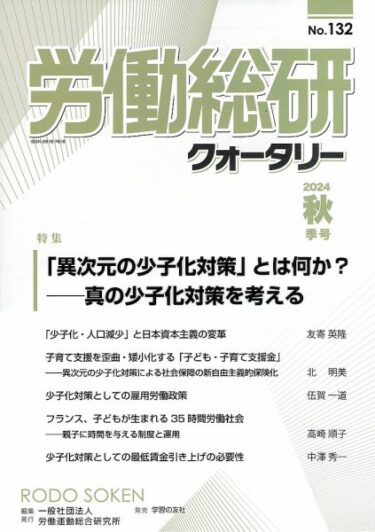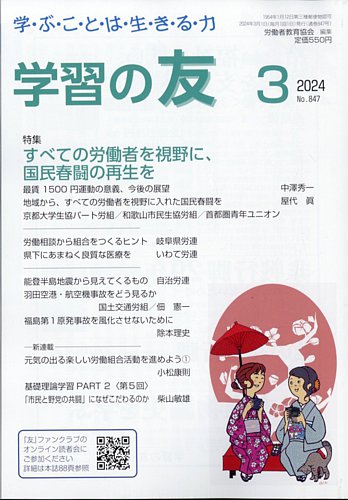中澤 秀一(2023)「コロナ禍における最低賃金改定をめぐる動向」『女性労働研究』第67号(2023年)pp.127-133に加筆
2023年7月28日、中央最低賃金審議会で今年の最低賃金の目安額が示されました。そのことをうけて、中澤秀一さん(静岡県立大学短期大学部)から論文が届きました。女性労働問題研究会が発行する『女性労働研究』第67号(2023年3月発行)に掲載された論文に加筆をされた、最新情報を含む貴重な内容です。どうぞお読みください。
コロナ禍後の最賃改定をめぐる動向―23年改定をどうみるか
中澤秀一(静岡県立大学短期大学部)
はじめに
新型コロナウイルス感染症は社会的弱者により深刻な影響をもたらし、世界中で生活困窮に陥る人々が増大した。この対応策として世界的にも注目された政策が、最低賃金制度である。諸外国では「コロナだからこそ最低賃金を引き上げた」のに対して、2020年における日本政府の選択は「コロナをふまえて最低賃金を“凍結”」であった。果たして、この選択は正しかったのだろうか。必然的にその答えは翌年に出されることとなる。2021年はうって変わって大幅に引き上げる選択であった。コロナで打撃を受けた経済を回復させるためには、日本でもコロナだからこそ最賃を引き上げなければならなかったのである。前年の選択が間違っていたことの証左である。
その後のウクライナ情勢や急激な円安によって、ますます格差・貧困が深化・拡大する現局面において、対症療法ではなく、根治治療の策として最低賃金制度が果たす役割は大きいと筆者は考えている。本稿では、最低賃金(以下、最賃)を決定する場である中央最低賃金審議会から示された2022年度「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告」から公労使それぞれの主張を確認し、さらに2023年の最低賃金の改定について考えてみたい。まずは、コロナ禍が始まった2020年以降の最賃をめぐる動向を概観しておこう。
1.20~21年の最賃をめぐる動向
2020年4月、全国に緊急事態宣言が発出されて10日を経たずして、日本商工会議所など中小企業三団体が「最低賃金に関する要望」を公表する。同要望は、全国加重平均1000円すらも高すぎる目標であること、新型コロナがもたらした経済的危機を反映して企業にとって納得感がある水準を定めるべきであること、強制力のある最賃の引上げを政策的に用いるべきではないこと、生産性向上や取引適正化への支援等により中小企業・小規模事業者が自発的に賃上げできる環境を整備すべきであること等を柱としていた。この要望が政策に与えた影響は大きく、同年6月に開催された「全世代型社会保障検討会議」では、最賃“凍結”はやむなしの意見が大勢を占める。それをふまえて、中央最低賃金審議会(以下、中賃)は目安額の引き上げを示さなかった。その後、40もの地方最低賃金審議会(以下、地賃)が上乗せ答申を決定したのであるが、人口の多い東京や大阪の地賃は上乗せすることはなかったため、全国加重平均は901円から902円とわずか0.1%の引き上げにとどまったのである。
翌21年は、コロナ禍により経済が減退した反省をふまえて、一気に最賃引き上げに舵が切られる。3月、「経済財政諮問会議」に内閣府経済社会総合研究所の調査報告書「最低賃金引上げの中小企業の従業員数・付加価値額・労働生産性への影響に関する分析」が提示される。同報告書では、近年の最賃引き上げが中小企業の雇用、付加価値額、労働生産性に与える影響について、地域別・業種別パネルデータを活用した分析を行っており、最賃水準が中高位の地域では最賃引き上げによる雇用の増減は確認されなかった一方で、最も低い区分(最賃Dランク)の地域では雇用が有意に増加しているという結論が導き出されている。このときの「経済財政諮問会議」では、スウェーデン王立銀行経済学賞(通称、ノーベル経済学賞)を受賞したD・カードらによる最賃に関する有名な研究も紹介されており、同年の最賃引き上げは既定路線であった。結局、21年の最低賃金は前年度比3.1%、全国加重平均で902円から930円へと引き上げられた。
2.22年の最賃をめぐる動向
(1)二度の方向転換
2022年は、最賃をめぐって二度の方向転換がみられた。一度目の方向転換は、国際的ルールや法律に則った方向へのシフトである。岸田政権がめざす新しい資本主義に向けた重点投資分野の一つとして「人への投資」があるが、五月に開催された「新しい資本主義実現会議」では、この「人への投資」についての論点整理が行われた。ここでは「最低賃金については、ILO条約でも、使用者及び労働者が同数で、かつ、平等の条件で参加しなければならないとされていることに留意したプロセスを経るべきではないか」と盛り込まれた(傍点は引用者)。これは、使用者委員の主張が色濃く反映されてしまっている現在の審議会のありようを省みた姿勢と受け取れる。また、最低賃金額を決定する考慮要素(①労働者の生計費、②賃金、③通常の事業の賃金支払い能力)を改めて強調している点も、審議会での議論において、これらの考慮要素がきちんと検討されていない実態を省みたのではないか。このように最低賃金制度の正常化に向けて政府が取り組む姿勢をみせたことは評価できる。このような方針転換の背景にあったと考えられるのは、ESG投資である。現在、環境(Environment)や社会(Social)に配慮して事業を行っていて、適切な統治(Governance)がなされていない企業あるいは国からの投資離れが急速に進んでいる。「新しい資本主義」の実現を政治目標に掲げ、デジタル、グリーン、人への投資の3分野に重点を置く岸田政権としては、最賃のあり方についても配慮せざるを得なくなったのであろう。
ところが、最低賃金制度が正常化する前に、二度目の方向転換が行われた。同年6月、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現」が閣議決定された。このなかでは「スタートアップやグリーントランスフォーメーション、資産所得倍増について、複数年度にわたる具体的なプランを本年中に策定し、実行いたします」や「機動的なマクロ経済運営によって経済回復を実現しながら、新しい資本主義の実現に向けた計画的で重点的な投資や規制・制度改革を行い、成長と分配の好循環を実現する岸田内閣の経済財政政策の全体像を示しています」などが宣言されており、それまでの分配重視の方向性は転換され、明らかに成長重視へと再シフトするのである。二度目の方向転換をふまえて、22年の最賃改定は、それまで政府が掲げてきた引き上げ目標=3%を大きく逸脱しない範囲にとどまるのである。8月に中賃は、A・Bランクは31円の、C・Dランクは30円の、それぞれの引き上げの目安額を答申した。全体では、過去最大の引き上げ額31円(3.3%増)で、同年10月からの新しい最低賃金額は全国加重平均961円となった。過去最大とはいえ、2016年からの政府の引き上げ目標3%を大きく上回っているわけではなく、後述するように物価上昇にも見合わない引き上げである。22年、変わりかけた最低賃金制度は、結局大きく変わることはなかった。今後、どのような最低賃金制度のあり方がめざされるべきなのか、中賃が答申後に公表した報告書をもとに考えてみたい。
(2)公労使それぞれの見解
中賃からの目安額答申後、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告」(以下、目安小委員会報告)が公表された。目安小委員会報告では構成メンバーである公益委員、労働者委員、使用者委員、それぞれの見解を表明している。
1)労働者側見解
労働者委員の見解は要約すると、以下の通りである。①経済を成長軌道にのせるためには、「人への投資」が必要であり、その重要な要素が最賃である、②春闘での賃上げを最賃の引き上げにも波及させるべきである、③現在の最賃はワーキングプア水準であり生存権も確保できず、連合が公表している水準(連合リビングウェイジにもとづく水準で、最も低い県では950円を上回る[1])に引き上げるべきである、④中小企業が円滑に価格転嫁をできるように最賃引上げに向けた環境を整備することが重要である、⑤労働力人口の減少局面において、存続・発展に向けて賃上げを通じた人材確保に重きを置いている企業は採用時の賃金を引き上げている、⑥地域間の最賃格差をこれ以上放置すれば、労働力の流出により、地方・地域経済への悪影響があるとの懸念があり、地方はそのことに危機感を持っていることを中賃は受け止めるべきである、⑦「誰もが時給1000円」への通過点として、「平均1000円」への到達に向けてこれまで以上に前進する目安が必要であり、あわせて地域間格差の是正に向けてC・Dランクの底上げ・格差改善につながる目安を示すべきである。
果たして、めざされるべき最賃の水準=1000円は適切だといえるのだろうか。時給1000円ではフルタイムで働いたとしても、年収に換算して200万円程度である。働いても貧困=ワーキングプアに陥ることは明白である。筆者は、2015年から全国各地でマーケット・バスケット方式による最低生計費試算調査の監修を行っており、23年現在で27都道府県での結果を公表している。表1は、22年に公表した若年単身世帯(25歳の一人暮らしの若者)の結果である。20年以降では若者が普通の暮らしをするために必要な費用は月額24~26万円(税金や社会保険料込み)であった。これを時給に換算すると、少なくとも1500円になる。時給は労働時間によって変動するので、人間らしい労働時間、つまり適度な労働時間で換算してみると1600~1700円になる。つまり、時給1000円では低すぎるのである。労働者に寄り添った目標を掲げることが労働者委員の役割であるはずだ。
表1 最低生計費試算調査(25歳単身世帯)の結果(2022年公表分)
コロナ禍後の最賃改定をめぐる動向.png)
2)使用者側見解
使用者委員の見解を要約すると、以下の通りである。①新型コロナや急激な物価高騰、円安の進行、海外情勢等の影響を受けている中小企業の経営状況や、地域経済の実情を的確に読み取り、明確な根拠をもとに、納得感のある目安額を提示できるよう、最低賃金法第九条における三要素に基づいて慎重な審議を行うべき、②「生産性が向上し、賃上げの原資となる収益が拡大した企業が、自主的に賃上げする」という経済の好循環を機能させることが重要であり、スムーズな好循環の実現のため、中小企業に対する一層の支援を含め、さらなる生産性の向上や価格転嫁も含む取引環境の適正化への支援等の充実が不可欠である、③中小企業の賃金引き上げの実態を示している「賃金改定状況調査結果」の第四表を重視すべき、④経営を維持してきた企業の「通常の事業の賃金支払能力」を最も重視して審議していく必要がある。
中小企業に対する支援や、生産性の向上や価格転嫁も含む取引環境の適正化への支援等は最賃の大幅引き上げのための絶対の条件であり、この部分は納得できる。ただ、通常の事業の賃金支払い能力は、現行法においても考慮要素のなかの一つに過ぎず、必ずしも最も重視されるべき要素でないことは指摘しておきたい。2007年に法改正され、最低賃金法第9条に3項が追加されたのであるが、ここで労働者の生計費を特別に強調している点に注目すれば、三つの考慮要素において最も重視されるべきは労働者の生計費であることは言うまでもない。一日八時間働いても普通に暮らせない最低賃金は、人権侵害に他ならないからである。
3)公益委員見解
公益委員の見解には、最賃のありようが如実に表れている。まずは、「『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画』及び『新しい資本主義実行計画工程表』並びに『経済財政運営と改革の基本方針 2022』に配意しつつ、各種指標を総合的に勘案し、(中略)公益委員の見解を取りまとめたものである」と、政府の方針に従っていることを堂々と宣言するのである。先に述べたように、2016年から中賃は政府目標に沿った目安額を答申しており、独自性を発揮しているとは言い難い。また、地賃も近年は目安額に上乗せをするところが多いが、真摯な議論により十分審議を尽くしているとは言えず、中央から示された目安に縛られているのが実情である。
賃金に関しては、「第四表は、目安審議における重要な参考資料であり、同表における賃金上昇率を十分に考慮する必要がある」と、使用者委員と同様に公益委員もまた、中小企業の賃金引上げの実態を示している「賃金改定状況調査結果」の第四表を重要視する。確かに、見るべき指標の一つではあるが、一部の賃金引き上げの実態しか参考にしないのはおかしい。最賃が年々上昇するなかで、最低賃金近傍で働く労働者の数はますます増加している。最賃の影響を過少に評価しようとする姿勢は改めるべきである。
労働者の生計費に関しては、「関連する指標である消費者物価指数を見ると、『持家の帰属家賃を除く総合』は今年4月に3.0%、5月に2.9%、6月に2.8%(対前年同月比)となっており、とりわけ『基礎的支出項目』といった必需品的な支出項目については4%を超える上昇率となっている」と分析しているにもかかわらず、最低賃金引き上げ率は3.3%にとどまった。物価の上昇に追いついていないのである。それにもかかわらず、目安小委員会報告書の中で公益委員は、「結果として、三要素のうち、特に労働者の生計費を重視した目安額」であると述べるのである。22年10月の改定以降も消費者物価指数は対前年同月比で上昇を続けており、最賃は労働者の生計費の上昇に見合っていないのである。次回の改定(2023年10月)の前に再度の引き上げ改定を行わなければなかったのである。ちなみに、ドイツやフランスでは年間に複数回の最低賃金引き上げを実施しており、物価の上昇に柔軟に対処している。
ランク別の最賃格差については、「昨年度はAランクの地域を中心に雇用情勢が悪化していたこと等も踏まえて全ランク同額としたが、今年度はAランクにおいても足下では雇用情勢が改善していることから、A・Bランクは相対的に高い目安額とすることが適当であると考えられる。一方、地域間格差への配慮の観点から少なくとも地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き続き上昇させていく必要があること等も考慮すれば、A・BランクとC・Dランクの目安額の差は1円とすることが適当である」(下線は引用者)と説明しているが、最高額に対する最低額の比率が高くなれば、格差が縮小しているとの考え方に違和感がある。なぜならば、生活者にとって、比率ではなく、差額が意味を持つからである。例えば、A県=1000円、B県=800円の最賃格差は、A県に対するB県の比率で80%、差額で200円である。これがA県でプラス100円、B県でプラス90円と上昇すると、A県=1100円、B県=890円となるが、A県に対するB県の比率は約80.9%となり、格差は是正されたことになるが、両県の差額じたいは210円と拡大しているのである。B県の人はA県との格差が拡がったという実感であろう。
最後に公益委員は、「地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金の審議に際し、地域の経済・雇用の実態を見極めつつ、自主性を発揮することを期待する」と、地方での上乗せを容認する姿勢をみせている。中央と地方のそれぞれの審議会の役割とは何か、問い直される時期に来ているのかもしれない。
3.23年の最賃をめぐる動向
(1)8年ぶりの「政労使」会議
2023年3月、8年ぶりに政労使それぞれの代表が参加する「政労使の意見交換」(「政労使」会議)が開催された。同会議には、政府からは岸田首相、加藤勝信厚生労働大臣ら8名が、労働界代表として連合の芳野友子会長と清水秀行事務局長の2名が、経済界代表として経団連の十倉雅和会長、日本商工会議所の小林健会頭ら4名が出席した。同会議で岸田首相は、「全国加重平均1000円を達成することを含めて公労使三者構成の最低賃金審議会でしっかりと議論をいただきたい」と述べ、「地域間格差の是正を図るため、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げること」や「(全国加重平均)1000円達成後の最低賃金引上げの方針」についても触れている。6月に決定した「経済財政運営と改革の基本方針 2023」(骨太の方針2023)でも全国加重平均1000円が達成されることが前提となる書きぶりとなっており、23年の最賃改定は審議会での議論の以前に、全国加重平均1000円以上になることは誰の目にも明らかなことであった。
(2)43年ぶりのランク見直し
4月、中央最低賃金審議会は1978年の制度創設以来見直されることのなかった都道府県別のランク制度(ランク数)を4段階から3段階に減らすことを決定した。これは、地域間格差を縮小することが狙いであると考えられる。現行のランク制度では、A=6都府県、B=11府県、C=14道県、D=16県に区分されているのが、新ランク制度では、A=6都府県、B=28道府県、C=13県とした。
ランクの見直しを決定した「目安制度の在り方に関する全員協議会」はその報告のなかで、4ランクから3ランクに見直した理由として、①47都道府県の総合指数の差、分布状況に鑑みると、格差が縮小傾向であることから、ランク区分の数を減少させることに相当の理由があると考えられる、②ランク区分の数が多ければ、その分、ランクごとに目安額の差が生じ、地域別最低賃金額の差が開く可能性が高くなる、③2014年度以降、4ランクとしつつも、目安審議における検討の結果、目安額を3つまたは2つとした年度があり、目安額を4つ示すほどの差がつきづらくなっており、このため、最大3つの目安を示す構造となることで大きな混乱は生じにくく、かつ、ランクを減らすことの合理性もあると考えられる、④ランク数の変化による影響をできるだけ軽減するため、現行の4ランクから1つ減らした3ランクとする、以上の4点を挙げている。
いずれも説得力に欠ける理由である。地域間格差の解消が是であれば、世界標準である全国一律制に変えるべきである。たとえ一時的な混乱が起こったとしても、格差が解消されるのであれば、それは乗り越えなければならないことである。結局のところ、ランク制度は維持したいが、地域間格差を拡大させているという批判もかわさなければならないことから、3ランク制への移行に決着させたのだろう。
(3)全国加重平均1000円は達成されたが…
7月、中央最低賃金審議会は23年度の各都道府県の引上げ額の目安について、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円、全国加重平均で41円の引き上げ(4.3%増)を決定した(金額、率ともに過去最高)。仮に、目安どおりに各都道府県で引き上げが行われたとすると、全国加重平均1002円となり、政府が2015年より掲げてきた目標がようやく達成されたことになる。ただ、1000円を超えたといっても、先に述べたようにマーケット・バスケット方式による最低生計費試算調査からは、普通の暮らしに必要な時給は1500円以上である結果が出ている。時給1000円は、あまりに低い水準なのである。また、物価上昇の傾向は止まっていない。最低賃金の近傍で働く労働者にとって、4.3%の引き上げでは賃上げの実感は乏しいだろう。
また、今回の3ランクの間で1円ずつの格差が設けられたことも問題視されなければならない(筆者は、Cランクのほうで引き上げ額が高くなることを予想していた)。目安どおりの改定だった場合には、最高額と最低額の格差は221円に拡大する。中賃の示した目安が格差を拡大させたことは、地域間格差の縮小のために3ランクに移行したことの意義を失わせる(おそらく、8月以降の地方最低賃金審議会での議論において、Cランクでは上乗せが決定されるだろうが)。
むすびに―新時代の最低賃金制度
日本における最低賃金の歴史を振り返ってみると、外国からの低賃金批判と労働力不足により初任給高騰の懸念から1959年に最低賃金法が制定され(業者間協定方式でスタート)、高度経済成長と春闘による大幅賃上げにより1968年に審議会方式に修正され、高度経済成長の終焉とオイルショックによる物価高や全国一律化の動きの高揚を背景にして、1978年にA~Dランク別の目安制度が導入され、生活保護との逆転現象を解消するために、2007年に法改正が行われた。このように、時代の要請に応じて最低賃金制度は、修正を繰り返してきたのである。
四半世紀にわたって下がり続ける賃金、労働者の4割におよぶ非正規雇用、中間層の下落による格差の拡大、コロナ禍が明らかにした矛盾(溜めのない社会、人口集中の危うさ、社会を支えるエッセンシャルワーカー・ケア労働者に報いていない賃金、出生数の低下…)等、これらの状況に最低賃金制度は対応しているのだろうか。いま、最賃は新しい時代の要請に応えられるよう、修正が迫られており、それは「全国どこでも最賃1500円」なのである。
(注)
[1] 連合リビングウェイジとは、日本労働組合連合会(連合)が労働者が健康で文化的な生活ができ、労働力を再生産し社会的体裁を保持するために最低限必要な賃金水準を算出したもの。五年おきに改定しており、2021年の改定では、外部有識者の監修のもと、試算方法の見直し等を行っている。まず埼玉県さいたま市をモデル地域に設定し、小売物価統計調査データ等をもとに各都道府県の金額へ換算した「都道府県別リビングウェイジ」をまとめている。
(参考文献)
黒田兼一(2022)「いま最低賃金制度改革の大手術のとき」『月刊全労連』No.305
中澤秀一さんの投稿論文は、こちらから。