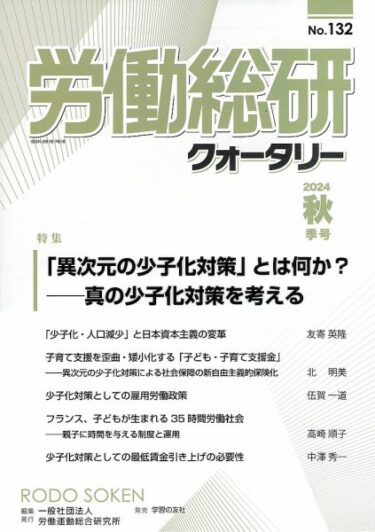中澤秀一「最賃 1500 円運動の意義、今後の展望」『学習の友』第847号(2024年3月号)pp.14-21
学習の友社が発行する『学習の友』第847号(2024年3月号)に掲載された中澤秀一さん(静岡県立大学短期大学部)による論文の転載です。どうぞお読みください。
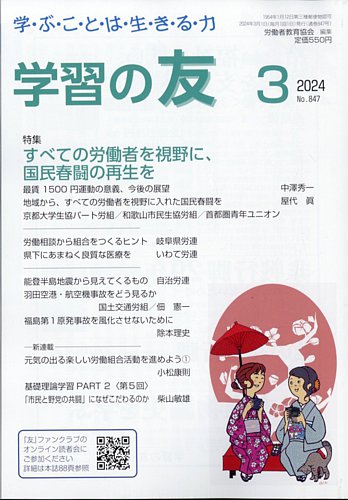
はじめに
2023年10月、安倍政権が2015年に掲げた最低賃金の全国加重平均1000円の目標がようやく達成されました。7月の中央最低賃金審議会による目安答申の時点で全国加重平均額=1002円となり、初めて1000円を突破しました。さらに、その後の各地の地方最低賃金審議会での上乗せが相次ぎ、最終的には引き上げ率は4.5%、引き上げ額は43円となり、全国加重平均額=1004円となりました。安倍政権の目標が掲げられた時の全国加重平均額は780円でしたから、この8年間で28.7%上昇したことになります。
2000年代初頭からみれば、最低賃金の水準は急速に引き上げられましたが、先進各国をみれば、まだまだ低水準ですし、都道府県別格差が大きいことなど、最低賃金制度にはまだまだ問題が残されています。本稿では、最低賃金制度の改革に奮闘してきた近年の労働運動を総括するとともに、今後の展望についても考えてみたいと思います。
物価高騰に追いつかない賃金
23年の全国消費者物価指数(2020年=100、生鮮食品を除く)は、前年に比べ3.1%上昇の105.2でした。1982年以来、41年ぶりの高い上昇率です。背景にあるのは、2022年2月に始まるロシアによるウクライナへの侵攻と、同じく2022年の3月に始まる円安でした。前者により原油や穀物の価格が、後者により原油や穀物以外の輸入品の価格も高騰しました。図1は、最低賃金審議会でも参考にされている持家の帰属家賃を除く消費者物価の総合指数の推移です。2022年から急激に上昇し始めていることが確認できます。また、毎月勤労統計調査(厚労省)によると、2023年11月における一人当たりの実質賃金は前年同月比3.0%減で、20カ月連続でマイナスとなりました。
このように物価高騰に賃金上昇が追いつかない状況が続いており、労働者の生活不安につながっています。生活不安を解消し、誰もが普通に暮らせるようにするためには賃金の底上げが必要です。かねてより労働運動は最賃1500円を要求し続けてきましたが、この物価高騰により最賃1500円がますます説得力をもってきたと言えるでしょう。以下、最賃1500円の意義、また実現のためには何が求められるのかを考えてみましょう。
図1 全国消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く消費者物価の総合)推移
(2020年=100)
図1 全国消費者物価指数推移.png)
最賃1500円の根拠
新宿区労連・新宿一般労働組合が2012年に最賃引き上げデモを始めた当時は、最賃1000円の要求でした。しかし、毎月デモを重ねる中で「1000円では足りないのではないか」との声があがり始め、2014年からは1400円の要求を掲げるようになり、翌2015年からは1500円にさらに引き上げられました。初めは「高すぎる要求」とみなされていた最賃1500円の要求はだんだんと世間に浸透するようになり、いまや社会の常識になったと言えるでしょう。その証拠に、2023年全国加重平均1000円を達成した岸田首相が、次なる目標として「2030年代半ばまでに1500円」を掲げたのです。もはや、1500円という数字を無視することができなくなっているのです。
さて、この最賃1500円という数字の根拠の一つとなっているのが、最低生計費試算調査(以下、生計費調査)です。全労連とその地域組織によって取り組まれてきた生計費調査は全国各地で実施されており、労働運動の要求の後押しをしています。筆者はそのうち27都道府県で実施された生計費調査の監修に2015年から関わっており、各地で調査結果を公表しています(表1参照)。調査から見出された発見は、①労働者が普通に暮らすためには月額24~26万円(税・社会保険料込み)が必要であること、②労働者の生計費には全国どこでも大きな差がないこと等でした。これらの発見は、労働運動のさまざまな場面で活用されています。詳細については、『日本の科学者』2023年12月号掲載の拙稿「最低賃金の全国一律1500円の根拠・意義・展望―最低生計費調査からわかったこと」を参照してください(下記、URLよりダウンロード可能)。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsci/58/12/58_42/_article/-char/ja
表1 最低生計費試算調査の結果(25歳単身世帯) (円)
| 自治体名 | 盛岡市 | 水戸市 | 東京都北区 | 新潟市 | 岐阜市 | 京都市 | 岡山市 | 高知市 | 佐賀市 | 那覇市 | ||
| 調査年 | 2022年 | 2020年 | 2019年 | 2015年 | 2022年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 | 2019年 | 2020年 | ||
| 消 費 支 出 | 186,717 | 179,910 | 179,804 | 177,018 | 176,737 | 178,390 | 180,404 | 183,688 | 178,127 | 179,439 | ||
| 食 費 | 47,242 | 41,967 | 44,361 | 39,597 | 44,872 | 44,441 | 40,333 | 45,423 | 39,025 | 41,266 | ||
| 住 居 費 | 37,000 | 36,458 | 57,292 | 38,000 | 38,000 | 41,667 | 35,417 | 33,000 | 34,500 | 36,458 | ||
| 水道・光熱 | 11,614 | 7,546 | 6,955 | 11,064 | 7,874 | 7,419 | 7,273 | 8,710 | 8,150 | 8,764 | ||
| 家具・家事用品 | 3,932 | 3,265 | 2,540 | 3,765 | 3,058 | 3,836 | 4,032 | 3,247 | 3,561 | 3,826 | ||
| 被服・履物 | 7,144 | 8,440 | 6,806 | 6,951 | 7,748 | 5,921 | 6,575 | 6,638 | 5,635 | 5,021 | ||
| 保健医療 | 2,636 | 1,002 | 1,009 | 4,188 | 1,501 | 1,137 | 1,094 | 1,506 | 1,184 | 1,142 | ||
| 交通・通信 | 36,057 | 29,990 | 12,075 | 40,335 | 34,993 | 18,612 | 33,384 | 37,467 | 41,856 | 33,794 | ||
| 教養・娯楽 | 19,988 | 28,534 | 25,577 | 14,970 | 20,390 | 27,510 | 25,454 | 26,070 | 25,964 | 25,620 | ||
| そ の 他 | 20,105 | 22,708 | 23,189 | 18,148 | 18,301 | 27,847 | 26,842 | 21,627 | 18,252 | 23,548 | ||
| 非消費支出 | 52,686 | 55,177 | 51,938 | 47,287 | 53,422 | 49,595 | 50,107 | 47,711 | 46,045 | 48,977 | ||
| 予 備 費 | 18,600 | 17,900 | 17,900 | 17,700 | 17,600 | 17,800 | 18,000 | 18,300 | 17,800 | 17,900 | ||
| 最低生計費 (月額) |
税抜 | 205,317 | 197,810 | 197,704 | 194,718 | 194,337 | 196,190 | 198,404 | 201,988 | 195,927 | 197,339 | |
| 税込 | 258,003 | 252,987 | 249,642 | 242,005 | 247,759 | 245,785 | 248,511 | 249,699 | 241,972 | 246,316 | ||
| 年額(税込) | 3,096,036 | 3,035,844 | 2,995,704 | 2,904,060 | 2,973,108 | 2,949,420 | 2,982,132 | 2,996,388 | 2,903,664 | 2,955,792 | ||
| 必要最低賃金額A(173.8時間換算) | 1,484 | 1,456 | 1,436 | 1,392 | 1,426 | 1,414 | 1,430 | 1,437 | 1,392 | 1,417 | ||
| 必要最低賃金額B(150時間換算) | 1,720 | 1,687 | 1,664 | 1,613 | 1,652 | 1,639 | 1,657 | 1,665 | 1,613 | 1,642 | ||
| 参考:最低賃金額(23年10月~) | 893 | 953 | 1,113 | 931 | 950 | 1,008 | 932 | 897 | 900 | 896 | ||
最低賃金制度の存在意義
最低賃金制度について厚生労働省では、「最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。」と説明しています。いちおう、「最低賃金制度とは何たるか」を説明していますが、これでは最低賃金制度の本質、最低賃金が存在する意義については何ひとつ理解できません。
労働基準法の第1条に「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」と定めているように、賃金を含めて労働条件とは、すべての労働者が人間らしく生活することが可能でなければなりません。したがって、最低賃金で人間らしく生活できる=普通に暮らせることが強調されなければならないのです。不当に低い賃金しか支払わない使用者にペナルティを課して、事業の公正な競争を確保することに最低賃金制度の本質があるのではなく、働けば普通に暮らせるという生計費原則をすべての労働者に貫かせることや仕事の価値に応じた賃金が労働者に支払われることに制度の本質や存在意義があるのです。ところが、現在の最低賃金制度にはそういったことが欠落しています。フルタイムで働いたとしても貧困に陥ってしまうのは、人権侵害にほかなりません。最賃運動は、あたりまえの働く原則や人権が守られるべきであることを社会や政治に問うているのです。
普通に暮らすための費用を可視化する
先に述べたように、労働者が普通に暮らすためには月額24~26万円(税・社会保険料込み)が必要であることが生計費調査の結果から試算されています。本来であれば、最低賃金法第9条で定められた最低賃金の水準を決定する考慮3要素である、①労働者の生計費、②(地域における労働者の)賃金、③通常の事業の支払い能力が、きちんと検証されなければなりません。けれども、最低賃金を決定する場である最低賃金審議会では、これらの考慮要素がきちんと検証されているとは言いがたいのです。
審議会に提出されている①労働者の生計費に関する資料は、「標準生計費」です。この標準生計費は、人事院が毎年国家公務員の給与勧告を行う際に、参考資料として算定するもので、総務省によると標準生計費の位置づけは、国民の「平均的な生活費」です。また、各都道府県の人事委員会もそれぞれ標準生計費を算出しており、こちらは地方公務員の給与勧告を行う際の参考資料にもなっています。標準生計費の算定方法は、簡単に言えば政府統計における「並数」階層の費目別支出額をベースに試算しています。並数(モード)とは、最も度数の多い数字のことです。表2および表3をみると、標準生計費が「平均的な生活費」を思えないほどの低い水準であることは明らかです。また、たった1年違うだけでかなり変動があることも確認できます。なお、人事院は標準生計費に関する算定過程の詳細をオープンにしていません。国民・労働者の生活を左右する重要な数字をブラックボックスのなかで算定しているのは問題があると言わざるを得ません。その点、生計費調査の試算はオープンにされており、普通に暮らすための費用が目に見えるようになっていて、数字にとても説得力があるのです。
表2 令和5(2023)年4月 標準生計費 表3 令和4(2022)年4月 標準生計費
| 世帯人員
費目 |
1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 世帯人員
費目 |
1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | |
| 食料費 | 33,220 | 33,500 | 52,750 | 72,000 | 91,240 | 食料費 | 31,020 | 39,320 | 50,360 | 61,390 | 72,430 | |
| 住居関係費 | 46,640 | 49,610 | 45,080 | 40,550 | 36,020 | 住居関係費 | 44,710 | 79,300 | 63,280 | 47,260 | 31,240 | |
| 被服・履物費 | 5,760 | 3,920 | 6,340 | 8,760 | 11,180 | 被服・履物費 | 5,780 | 3,990 | 6,240 | 8,490 | 10,740 | |
| 雑費Ⅰ | 24,830 | 25,830 | 49,460 | 73,090 | 96,720 | 雑費Ⅰ | 22,620 | 37,190 | 54,470 | 69,760 | 86,030 | |
| 雑費Ⅱ | 10,460 | 12,220 | 16,990 | 21,770 | 26,540 | 雑費Ⅱ | 10,350 | 19,130 | 22,740 | 26,340 | 29,950 | |
| 計 | 120,910 | 125,080 | 170,620 | 216,170 | 261,700 | 計 | 114,480 | 178,930 | 196,090 | 213,240 | 230,390 |
最低賃金法では、3つの要素のうちで労働者の生計費を最も重視しており、本来は国なり自治体なりが調査を実施し、生計費を試算しなければならないはずです。公的な調査が実施されていないなかで、生計費調査の試算結果は(とくに地方の審議会において)影響を及ぼしたのではないでしょうか。少なくとも最賃運動に確信をもたらしたことは事実です。
最賃に「支払い能力論」は不要
これまで審議会では、最低賃金の水準の決定に際して「賃金改定状況調査」の結果を重視してきました。この調査は、審議会における最低賃金の決定、改正等の審議に資するよう、労働者の賃金改定の状況等を把握するために実施している調査で、調査対象となるのは、全国の民営事業所のうち、常用労働者数が30人未満の企業に属し、1年以上継続して事業を営んでいる事業所です。審議会では、この賃金改定状況調査のなかでも、中小零細企業で働く労働者の賃上げ率を示した「第4表」を最重視しています。考慮要素のなかに地域における労働者の賃金があるわけですから、「相場論」が入ることじたいに問題はありません。けれども、「第4表」に偏重するのはいささか問題があるでしょう。なお、2016年以降の最低賃金の改定については、審議会は政府の方針に従う傾向が強く、これまで「第4表」を最重視してきたこととの整合性はとれていません。
ただ、ここで本当に問題視しなければならないのは、最低賃金を決定する審議会の議論において「支払い能力論」が強い影響力をもっていることです。最低賃金の決定において「支払い能力論」が認められると、「企業に支払い能力がなければ、労働者の生活を犠牲にしても構わない」がまかり通ってしまいます。「支払い能力論」は排除されなければなりません。もちろん、中小零細企業のなかには、最低賃金の引き上げには対応できないところもあるでしょう。労働者の生活を守るために最低賃金を引き上げると同時に、体力のない企業に対して支援をするのが国の責務です。最賃運動は個別企業に最低賃金の引き上げを求めてはいません。政治に対して最低賃金を引き上げられる環境を整えることを求めているのです。最賃運動では、具体的に中小企業への直接の助成金、社会保険料の減免、公正取引の実現などが挙げています。そして、これらの支援策を実現するためにはまとまった財源が必要になるでしょう。しかし、そういったことに財源を回すことにより、賃金が底上げされて格差が是正され、貧困を減らすことにつながるのです。そのような意味で最低賃金制度とは所得再分配策であるのです。
今後も中小企業支援の視点は、最賃運動が経営者からの支持を得るために必要となるでしょう。ただ、これまで挙げられてきた支援だけでは不十分ではないでしょうか。なぜならば、公正な取引が実現したとしても、最低賃金の引き上げ分を価格に転嫁できるとは限らないからです。価格への転嫁には、実際には製品やサービスの質、ブランド力なども大きく関わっています。質やブランド力を向上させられるような、中小企業の潜在力を引き出す支援策も必要であると考えられます。
最賃1500円で個人単位へ
23年の最低賃金をめぐる動向で注目すべきものに「年収の壁・支援強化パッケージ」があります。まず「106万円の壁」は税制上の壁で、パート労働者やアルバイトが年収106万円以上になると、厚生年金や健康保険に加入しなければならず、保険料が徴収されると手取りが減ってしまうので「壁」を越えないように労働時間を調整する傾向があります。一方、「130万円の壁」は社会保険制度上の壁で、被扶養者の年収が130万円以上になると、配偶者の扶養から外れて、自ら年金保険料や健康保険料などを納める義務が生じるので、やはり「壁」を越えないように調整する傾向がありました。いくら最低賃金を引き上げても、このような就労調整が行われると、労働力不足は一向に解消されません。したがって、「壁」を越えても手取りが減らない、あるいは引き続き被扶養者認定が受けられる仕組みを設けたのです。
日本では、パート労働者やアルバイトは被扶養者であり、かつ「家計補助的な就労」に従事していると決めつけられ、世帯の生計を維持しているわけではないので低賃金が当然とされてきました。その結果、最低賃金は「壁」の枠内に収まるような低い水準に抑えられたのです。多くの場合、パート労働者は女性であり、女性には不当に低賃金が押し付けられ、男女間の賃金格差の要因ともなりました。被扶養者であるから低賃金で良いという考え方は認められません。すべての個人が自立できる賃金、つまり最賃1500円でなければなりません。そのために税や社会保障の「壁」の枠組みは撤廃されて、個人単位化に移行すべきなのです。今回の「年収の壁・支援強化パッケージ」の適用を受けた世帯は、一時的には得をしているように思えるかもしれません。しかし、結局のところ「檻」の中に閉じこもることで個人の自立を遠ざけて、男女格差を温存させてしまったと考えるべきでしょう。
最賃1500円をベースに重層的な賃金規制
最賃1500円は高すぎるという意見はあまり聞かれなくなってきた一方で、むしろそれでは低すぎるという意見のほうが耳に届くようになってきました。確かに、生計費調査の結果でも、月労働時間を150時間に設定すると1600円~1700円の時給額になっていますし(表1参照)、すでに時給1500円を上回っている組合にとっては物足りないでしょう。最賃1500円とは、あくまで最低限(ミニマム)の目標であり、労働運動としてもっと高いところに目標を設定すればよいのです。つまり、どんなに低熟練の仕事であっても、普通に暮らせる最賃1500円が保障され、さらに熟練を必要とする仕事、専門的な知識・技能を有する仕事に対しては、それに見合った賃金が支払われるべきであり、それは1700円かもしれないし、あるいは2000円なのかもしれないのです。イメージすると、ベースに全国一律最賃1500円があり、その上に産業別(特定)最賃や公契約に関する労働者の賃金があります。さらにその上に企業別の最低賃金があり、こちらは個別の交渉でより高い目標設定がめざされるべきでしょう。これらの「最賃」は個々独立して存在しているのではなく、連動しており、ベースの全国一律最賃1500円が岩盤となり、その礎(いしずえ)の上に他の最賃が築かれていくということです。
ここで重要なのは連動していることです。その意識がないと、個々の組織は最賃運動に取り組めないでしょう。最賃運動は、まだまだ労働運動のメインストリームではありません。最低賃金が変わることで社会が変わり、やがては自分たちの職場も変わってくるのです。最低賃金は、「自分には関係のない賃金」ではなく、「自分にも関係のある賃金」であるという意識が広がれば、いまとは違う展望が見えてくるのではないでしょうか。
おわりに
最賃運動の目標には、主に本稿で取り上げた最賃1500円のほかに、全国一律制度の確立があります。さいごに、最低賃金の格差について触れておきましょう。2023年はランク制度創設以降初めての見直しが行われました。これまで目安額は全国47都道府県を4ランクに分けて、引き上げ額に差をつけてきました。つまり、高いランクほど引き上げ額を高く設定してきた結果、2006年と比べると最高額と最低額の差は約2倍に拡大しています。この最低賃金の格差が、人口流出をはじめする都市と地方との経済格差につながると運動は批判してきました。これまで審議会は頑なにランク制度を変えてきませんでしたが、4月にランク数の4ランクから3ランクへの変更を決定したのです。明言はされていませんが、かねてから運動の成果であることは間違いないでしょう。根拠(エビデンス)をもとに運動を展開すれば、必ず成果がもたらされるのです。
政策は、政治的力関係で決まるものです。どんなに正しいことを主張していても、それが政治に届かなければ、なかなか実現には結び付きません。今回のランク制度を変えさせた背景には、地方における地道な政治への働きかけがありました。今後もターゲットを見定めた戦略が重要となるでしょう。もちろん、そのためには社会の共感を得ることが大切なことは言うまでもありません。
(関連情報)
中澤秀一さんのNAVIへの投稿はこちらから。
本文中で紹介されている下記の原稿もぜひお読みください。
中澤秀一(2023)「最低賃金の全国一律1500円の根拠・意義・展望──最低生計費調査からわかったこと」『日本の科学者』第58巻第12号(2023年12月号)pp.714-720
「最低賃金の全国一律1500円の根拠・意義・展望──最低生計費調査からわかったこと」『日本の科学者』第58巻第12号(2023年12月号)pp.714-720.jpg)


-375x403.png)