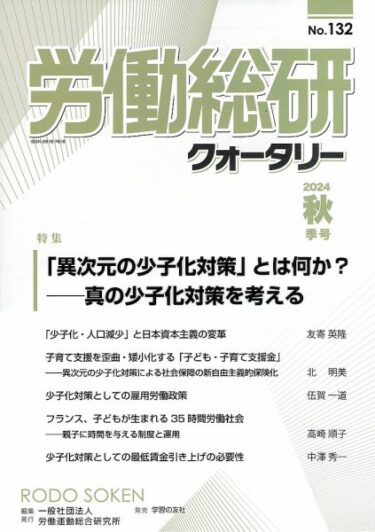中澤秀一(2024)「最低規制に関する考察──最低賃金制度を中心に」公益財団法人日本医療総合研究所編集・発行『国民医療』第362号(2024年夏季号)pp.40-49
最低規制に関する考察―最低賃金制度を中心に
はじめに―問題意識
2008年末、リーマン・ショックの影響による派遣切りで住まいを失った生活困窮者が、少しでも安心して年を越せるようにと日比谷公園に「年越し派遣村」が設置された。このときの「村長」を務めた湯浅誠は、憲法で保障されている必要最低限の生活を維持するための様々なセーフティーネットが機能しておらず、いったん足を滑らせてしまうとどのセーフティーネットにも引っかからずに底まで滑り落ちてしまうような日本の実態を「すべり台社会」と称した。日本は最低規制(最低限のルール)が確立されていない社会であると言えるだろう。図1は、湯浅の概念を図に示したものである。セーフティーネットについて論じる際に、最後のセーフティーネットである生活保護制度については、その捕捉率の低さなど諸問題が指摘されてきたのに対して、“最初”にして最も包括的なセーフティーネットとも言える賃金と雇用の保障については、所与の条件とされてきた感がある。
資本制社会における生活原則は自助原則(自己責任原則)である。ただし、自助の前提条件として、雇用と賃金とが保障されていなければならない。1990年代半ば以降に急速に進んだ雇用の劣化は「労働しても生活できない」労働者を大量に生み出し、自助の前提条件を取り崩してきた。そして、そのことが社会保障制度をも危うくしていることを重く見るべきである。
本稿では、“最初”にして最も包括的なセーフティーネットの一つである最低賃金制度について、日本独自の問題点を指摘するとともに、最低規制の確立に向けた展望を論じてみたい。
図1 「すべり台社会」日本
何層にも張られているセーフティーネットは機能不全

(出所)2009年5月16日開催パネルディスカッション「貧困と監獄―厳罰化を生む『すべり台社会』」湯浅誠氏発言資料をもとに筆者作成。
身近になってきた最低賃金
最低賃金とはどんな制度なのか?教科書どおりの説明ならば、「国が法律で賃金の最低限度額を定め、使用者はこの金額以上の賃金を支払わなければならない制度」である。最低規制の岩盤とも言える最低賃金制度は、これまで労働者にとってそれほど重要な制度とは見なされてはこなかった。なぜならば、多くの労働者にとってあまり「身近な賃金」ではなかったからである。図2は、2000年以降の最低賃金の全国加重平均額とその変化率の推移である。かつては、毎年1円か2円しか上がらず、ほとんどの労働者の生活に影響を及ぼすようなことはなかった(ちなみに、2006年の全国加重平均額は673円)。ところが、2000年代半ば以降から最低賃金額が急速に上昇し始めるようになる。その背景の一つに2007年の最低賃金法改正の影響がある。最低賃金額と生活保護基準との逆転現象が問題視され、最低賃金の考慮3要素である労働者の生計費が重視されるようになったからである[1]。それでもしばらくの間は、年率3%未満の引き上げ率にとどまっていた。最低賃金額がさらに急上昇したのは、2015年に安倍政権が掲げた政治的目標であったからである。景気回復を目的に賃金の底上げを図るため、できるだけ速やかに最低賃金を「全国加重平均1,000円」にまで引き上げるとの目標を掲げた。翌年以降ほぼ年率3%以上の引き上げが続き、2023年には全国加重平均で4.5%(金額にして43円)引き上げられて、全国加重平均額は1,004円となり「全国加重平均1,000円」の目標が達成された。
このように急速に引き上げられ、より身近になった最低賃金であるが、まだまだ重大な問題点が解決されぬまま取り残されている。
図2 最低賃金の全国加重平均額および引き上げ率の推移
(円)

(注)2009年は前年のリーマン・ショック、2011年は東日本大震災、2020年は新型コロナウイルスの影響により引き上げ率は抑えられている。
最低賃金制度が抱える問題
日本の最低賃金制度はいくつかの問題点を抱えている。本稿では、筆者が監修を担当した最低生計費試算調査(以下、生計費調査)の結果から次の2点を指摘しておきたい[2]。
第一の問題点は、1日8時間週40時間フルタイムで働いたとしても、普通には暮らすことができないほど低額に抑えられていることである(貧困最賃の問題)。現在、生計費調査からは、25歳の若者がひとり暮らしをするには、月額約24~26万円(税・社会保険料込み)必要であるという結果が出ている。現在の最低賃金の加重平均額は1,004円だが、1日8時間週40時間月160時間働いたとしても、約16万円である。ここから税金や社会保険料を差し引くと、手取りは12万円ほどになり生活保護基準と大差はない。限りなくワーキング・プアに近接した状態である。労働しても生活できない現実がここにある。
第二の問題点は、地域別最低賃金制度として47都道府県別に最低賃金額が定められており、地域間に根拠のない格差がつけられていることである(格差最賃の問題)。大都市圏が存在する都府県(Aランク)は金額が高く設定されているのに対して、人口の少ない地方(Cランクや旧Dランク)では低く設定されている。現在の最高額1,113円(東京都)と最低額893円(岩手県)とでは220円の格差が存在している。このような都道府県別の最低賃金の格差が容認されているのは、「大都市圏は家賃や物価が高く生活費がかかるのに対して、地方では反対に物価が安いので生活費があまりかからない」という“言説”が信じられてきたからである。本当に最低生計費は都道府県ごと大きく異なっているのだろうか。全国各地で実施された生計費調査は、この“言説”を否定する。表1はほぼ同時期に調査が実施された、東京都北区(2019年実施)と沖縄県那覇市(2020年実施)の生計費を比較したものである。最低生計費はほとんど同じ水準にあることが確認できる。確かに、住居費に関しては、大都市圏のほうが高い。ところが、交通費は、電車、バスなどの公共交通機関が利用できる大都市圏のほうが低く抑えられるのだ。公共交通機関が発達していない地方では自動車が通勤、買い物、通院、レジャーなどの必需品であり、ガソリン代、駐車場代、メンテナンス費を含めて生計費を押し上げる家計構造となっている[3]。結局のところ、住居費と交通費はトレードオフの関係にあり、全国どこでも生計費は大きく変わらないのだ。
先述したとおり、政策的に最低賃金額が大幅に引き上げられたてきたことにより、貧困最賃の問題は(まだまだ不十分であるが)ゆっくりと改善の方向に向かっているのに対して、格差最賃の問題は解消されていない。なぜならば、Aランクは引き上げ額を高く設定し、反対にC(旧D)ランクでは引き上げ額を抑制してきたので、ランク間の格差は2000年代初頭の2倍以上に拡大した。現在、最低賃金の格差は高止まりの状態にあると言ってよいだろう。
表1 東京と沖縄の最低生計費の比較
| 25歳男性 | 25歳男性 | |
| 東京都北区 | 沖縄県那覇市 | |
| 消費支出 | 179,804 | 179,439 |
| 食費 | 44,361 | 41,266 |
| 住居費 | 57,292 | 36,458 |
| 光熱・水道 | 6,955 | 8,764 |
| 家具・家事用品 | 2,540 | 3,826 |
| 被服・履物 | 6,806 | 5,021 |
| 保健医療 | 1,009 | 1,142 |
| 交通・通信 | 12,075 | 33,794 |
| 教養娯楽 | 25,577 | 25,620 |
| その他 | 23,189 | 23,548 |
| 非消費支出 | 51,938 | 48,977 |
| 予備費 | 17,900 | 17,900 |
| 最低生計費 | 197,704 | 197,339 |
| 税込み月額 | 249,642 | 246,316 |
| 税込み年額 | 2,995,704 | 2,955,792 |
| 最低賃金額(2023年) | 1,113円 | 896円 |
(出所)全国労働組合総連合調べ。
地域別最低賃金がもたらす弊害
前章でみたように地域別最低賃金制度は、地方に“格付け”を行う制度である。この“格付け”がさまざまな弊害をもたらしていることを確認してみたい。
第一の弊害は、地方からの人口流出の要因となっていることである。分かりやすいのが、川一本、道一本隔てた県境で生じる時給格差である。一例を紹介してみたい。静岡県熱海市と神奈川県湯河原町の境に千歳川という小さな川が流れている。全国チェーン展開するコンビニが募集しているアルバイトの時給格差は、熱海市と湯河原町では128円以上に達している(最低賃金が静岡県=984円、神奈川県=1,112円)。これは多くのコンビニをはじめとする全国チェーン展開する店舗のアルバイトの募集時給が最低賃金に張り付いているからである。当然、時給が高いほうに労働者は集中する。静岡県では人口の社会減が大きな問題となっているが、これだけの時給格差があれば年収に換算すると20~30万円くらい違ってくるので、若年層を中心に神奈川県や東京都に人口が流出するのは致し方ないことである。このような隣接する都道府県間の時給格差は、全国いたるところで見られる現象である。地方にとって人口流出は、地方経済の活力を奪い、自治体の税収は減収となり、まさに死活問題となっている。このことは言うまでもなく社会保障財政にも大きな影響を及ぼしている。
第二の弊害は、地方の賃金相場を引き下げてしまっていることである。先述したようにコンビニ等で働くパート・アルバイトなどの非正規労働者の賃金(時給)が最低賃金に張り付いている。同じ仕事をしているのにかかわらず、都道府県別に賃金が異なるのは不合理である。だが、これは非正規労働者に限った問題ではない。正規労働者を含めた一般労働者の都道府県別賃金格差にも大きな影響をもたらしていると考えられる。
図3および図4は、2023年における「医療・福祉」分野で働く一般労働者「きまって支給する現金給与額」(棒グラフ、左軸)と最低賃金額(折れ線グラフ、右軸)を都道府県別に示したものである(最低賃金については、2022年10月から2023年9月までの金額)。一般労働者の賃金の格差が、地域別最低賃金にリンクしていることが確認できる。「医療・福祉」分野の代表的な労働者である看護師や介護士は診療報酬、介護報酬など、公定価格で定められているので、本来であればこれほどの格差は生じないはずである。ところが、同一法人内での医療職や介護職の俸給表が都道府県別に定められており、一般労働者にも歴然とした地域間賃金格差が存在するのである。コロナ禍でケア労働者の待遇が不当に低いことが社会問題となったが、地方で働くケア労働者(後述するように特に女性)たちはさらに低い待遇に追いやられているのである。地域別最低賃金制度が、地方における労働者不足に拍車をかけていると言わざるを得ない。
また、賃金相場は女性のほうがより低い水準にある。一般労働者であっても「医療・福祉」分野で働く女性の賃金水準が、先述した月額24~26万円の最低生計費(=一人暮らしの若者が普通に暮らすために必要な費用)に届いていない県が少なからず存在するのだ。断っておくが、短時間労働者を除いた労働者のデータでの比較である。女性に対して不当とも言える低賃金を強いている実態がここにある。男性の仕事は、食べていける仕事であるのに対して、女性の仕事は、補助的な仕事、配偶者に扶養されていることを前提に食べていけなくてもよい仕事であると見なされてきたのである。「男性稼ぎ主モデル」の中に組み込まれた女性の賃金は、自立した個人の生計を想定していないのである。
図3 都道府県別、「医療・福祉」一般労働者「きまって支給する現金給与額」と最低賃金額(男性)
(千円) (円)

(出所)「令和5年 賃金構造基本統計調査」より作成
図4 都道府県別、「医療・福祉」一般労働者「きまって支給する現金給与額」と最低賃金額(女性)
(千円) (円)

(出所)図3と同じ。
そして、上記の弊害にも関連して地方で深刻となっているのが少子化問題である。出生数が80万人を割り込み、危機感を抱いた岸田政権は、異次元の少子化対策としてさまざまな子育て支援策を掲げている。ただ、いずれも子育てに対する支援であり、直接出生率の上昇に結びつくとは考えにくい。なぜならば、少子化問題の根本にあるのは、カップル数の減少だからである。図5は、婚姻件数と出生数の推移である。婚姻件数の減少に連動して出生数も減少している。非嫡出子の割合がスウェーデンやフランスなどと比較すると極端に低い日本は、婚姻するカップル数が増加しない限り出生数の上昇が見込めない国である。したがって、少子化対策はカップル数増に直結するような施策でなければならないのだ。
では、若者にとって家族形成が現実的になるためにはどのような状況になればよいのか。労働運動総合研究所が中心となって実施した若者調査では、賃金水準が高くなるほどか独立、家族形成の割合が高くなることが確認されている[4]。それでは、家族形成を現実的にするような賃金水準とはどの程度なのか。生計費調査は、若年単身世帯だけでなくさまざまな世帯類型でも子育て世帯の最低生計費試算を行っているが、30代カップルと子ども2人(小学生と幼児)の4人世帯では月額550~600万円(税・社会保険料込み)が必要であるとの試算が出ている[5]。後述するが、現在、最賃運動が求める最低賃金=1,500円が実現すれば、この賃金水準をクリアできるのである。1,500円×1800時間=270万円(年額)であり、カップル2人分だと540万円となり、4人世帯の最低生計費にほぼ到達するのである。
図5 婚姻件数と出生数の推移

(出所)「人口動態調査」より作成。
図6 都道府県別、人口千人あたり婚姻率と最低賃金額

(出所)「人口動態調査」より作成。
実際に、最低賃金が高い都府県では婚姻率が高くなる傾向にある。図6は、人口千人あたりの婚姻率を都道府県別に示したものであるが、全国平均=4.3を上回るのは、東京都=5.5、沖縄県=5.1、愛知県=4.9、大阪府=4.8、福岡県=4.5、神奈川県=4.4の6都府県に限られている。沖縄県だけは例外的で、残りは地域別の最低賃金額が高い都府県である。真剣に地方が少子化問題に取り組むならば、最低賃金の地域間格差の是正は避けて通ることはできないだろう。
改革の展望
現在、最低賃金の改革を求める運動は、目標として全国一律で少なくとも1,500円に引き上げることを掲げている。先述したように、全国各地で実施している生計費調査は、25歳の若者がひとり暮らしするためには1ヶ月24~26万円(税・社会保険料込)が必要であることを明らかにした。この金額を時給換算すると、あるべき最低賃金の水準がみえてくるのである。最低賃金審議会では月の労働時間を173.8時間で換算している。173.8時間とは、法定で最長となる所定労働時間で、1日8時間週40時間で、お盆休みもお正月もゴールデンウイークも関係なしに働き続けるという、健康でも文化的でもない労働時間である。この労働時間で換算すると、1,400円~1,500円になる。ただし、上記の理由からワーク・ライフ・バランスに配慮するならば、この換算は改めるべきである。かつて、政府が目標にしていた年間1800労働時間に相当する月の労働時間を150時間で換算すると1,600円~1,700円になる[6]。つまり、最低賃金の全国一律1,500円は決して過大な要求ではなく、むしろ控えめとも言える要求なのである。
生計費調査で想定したのは、「健康で文化的な最低限度の生活」=普通の暮らしである。この「最低限度の生活」は、一般的に「ギリギリ・カツカツの生活」というイメージが抱かれがちだが、本来は健康を維持・増進できるような生活の質や、自分の好きな趣味を楽しんだり、人付き合いができたりするような文化的なゆとりがそこには必要である。「健康で文化的な最低限度の生活」とは、「普通」や「人並み」に近い概念と考えるべきである。確かに、「普通」のとらえ方は人さまざまである。それでも、あえて「普通」とは何かを追及するのは、賃金や社会保障に最低限のルールを定めるためである。現在の最低賃金制度には「8時間働けば、普通に暮らせる」という当たり前のルールが確立されていないがために、「すべり台社会」になってしまっているのだ。いま、「普通」とは何かの社会的な合意を形成することは、最賃運動だけでなく、さまざまな要求運動にとっても取り組むべき重要な課題である。
おわりに―地域別の矛盾
本稿では、地域間格差を中心に日本の最低賃金制度の抱えている問題について論考を行った。地域別最低賃金制度は地域間格差を拡大しているとの批判を受けて、2023年4月にはランク制度創設以降初めての見直しが行われ、ランク数が4ランク(A~D)から3ランク(A~C)へと変更されている。一足飛びに全国一律制の実現は難しいが、今回の見直しは改革に向けた第一歩であると言ってもよいだろう。これまでの運動の成果として評価されるべきである。
さて、最低生計費に接点を有する最低規制には、最低賃金だけではなく、年金や生活保護がある。これらの制度は連動しており、いずれかが切り下げられれば、他の制度にその影響が及ぶことになる。したがって、運動面からみれば、個々に展開するよりも連帯したほうが効果的である。生計費調査の結果は、いずれの制度についても改革のエビデンスとなっている。今後も諸運動に活用していきたい。
最後に、問題提起を行って本稿を締めくくりたい。先に挙げた3つの最低規制のなかで、年金については全国一律であるが、最低賃金と生活保護は地域別に運用されている制度である。生活保護には級地区分が設けられており、この区分は消費支出額や課税対象所得の地域間格差の実態がその根拠にされている。しかし、生計費調査の結果は、生計費の地域間格差を否定することは先に述べたとおりである。そのほかにも公務員の地域手当など、さまざまな制度の中に地域間格差が内包されており、このことが地方に困難さを強いていることを改めて問題視するべきである。ナショナル・ミニマムの観点からすると、地域別の制度は矛盾を内包しており、生活保護についても全国一律の制度に変えていくべきではないだろうか。
[1] 当時、ジャーナリストとして取材にあたっていた竹信三恵子よると、この時期はワーキング・プアが深刻な社会問題となっていて、政権内に危機意識に近いものまで生まれていたと証言している。2004年に製造業派遣が解禁され、派遣労働者からの訴訟も相次ぎ、「男性世帯主」が一家を支える前提ですべてが成り立っていた日本社会で男性労働が危機に瀕し、とりわけ若い男性の雇用が劣化し、与党議員たちが地元の支持者から「うちの息子や娘が就職しても非正規しかない。この状態をどうしてくれる」と突き上げられる事態が起きていたそうである。実際、このあと政権交代が起こることになる。
[2] 最低生計費試算調査は、もともとは金澤誠一の監修のもとで全国労働組合総連合(全労連)およびその地方組織が主体となって実施されている。金澤調査は、算定方法として、マーケット・バスケット方式(全物量積み上げ方式)を採用している。主に労働組合員を対象者に「生活実態調査」と「持ち物財調査」からなる調査票を配布し、生活パターンや持ち物財の数量などを調べ、このデータをもとに世帯類型ごとに人間らしい生活を送るために必要な費用を算出する方法である。筆者も基本的にはこの方式を踏襲し、2015年から全国各地で最低生計費試算を行っている。これまでに集約したサンプルは約47600ケースで、このうち本稿の分析で利用されている若年単身世帯(一人暮らしをして若者)は約5000ケースとなっている。マーケット・バスケット方式の特徴は、人間らしく暮らすためには何が必要になるのか、現実の生活から遊離させないように配慮しながら、一つ一つ積み上げて算定していくところにある。配慮とは、「原則7割以上保有の品目=必需品」として最低生計費に組み入れる、「消費数量=下から3割の人が保有する数」等である。これらの配慮があるために、算定された最低生計費で実現される生活は、「あるべき」一定の理想ではあるが、少なくとも現実から大きくかけ離れた水準とはなっていないのである。また、金澤調査にはない独自の配慮として、合意形成会議がある。同会議は、当事者による積み上げ内容の精査である。その地域で暮らす者の“土地勘”や“肌感覚”を採り入れることで、監修者単独の生計費試算よりも客観性が担保されている。
[3] 地方の生活にとって自動車が必需品であるという事実は、社会保障制度、特に生活保護制度では見過ごされてきたことである。原則、被保護世帯には自家用車の所有が認められていないことは、憲法で認められた健康で文化的な最低限度の生活を保障していないことにつながりかねない。
[4] 労働運動総合研究所(2022)
[5] 中澤(2020a)
[6] 年間1800労働時間とは、1日8時間労働で、完全週休二日制、祝祭日の休業、年次有給休暇20日の完全取得で実現する労働時間である。現実的か否かは別にして、あるべき労働時間として実現されなければならない目標である。
(参考文献)
岩田正美(2010)「最低賃金制度と生活保護制度」『社会政策』第2巻第2号ミネルヴァ書房
岩永理恵(2011)『生活保護は最低生活をどう構想したか : 保護基準と実施要領の歴史分析』ミネルヴァ書房
金澤誠一編著(2009)『「現代の貧困」とナショナル・ミニマム』高菅出版
後藤道夫ほか編(2018)『最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし 『雇用破壊』を乗り越える』大月書店
中澤秀一(2018)「全国チェーン店時給調査」『労働総研クォータリー』No.109
中澤秀一(2020)「ディーセントワークの実現に向けた賃金と労働時間の展望」『女性労働研究』第64号
中澤秀一(2020)「生計費調査でみた子育て世代の『普通の暮らし』」『経済』No.294
中澤秀一(2023)「最低生計費調査の到達点―地方圏における最賃とは」『大分大学経済論集』第74巻第5・6号
中澤秀一(2023)「地方における若者の『普通の暮らし』を考える―最低生計費調査が示唆すること」『日本労働社会学会年報』第34号
中澤秀一(2023)「最低賃金の全国一律1500円の根拠・意義・展望―最低生計費調査からわかったこと」『日本の科学者』Vol.58本の泉社
中澤秀一(2024)「最低賃金制度の再考:生計費視点からの見直し」『社会政策』第15巻3号
中村和雄・脇田滋(2011)『「非正規」をなくす方法』新日本出版社
湯浅誠(2008)『反貧困―「すべり台社会」からの脱出』岩波書店
労働運動総合研究所(2022)「『若者の仕事と暮らしに関する実態調査』結果報告」『労働総研クォータリー』No.121





-375x266.png)